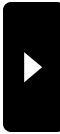2020年04月16日
腸にも美容にも!雑穀の健康パワー★レシピ「チョップドサラダボウル」
4月に入り、春の日差しが心地よい季節となりました
外出自粛が続きますが、体調管理には十分気をつけましょう
さて今回は「雑穀」についてのお話です
近年の健康志向の高まりから、市販のおにぎりやお弁当でも、玄米・雑穀・もち麦・大麦といった文字をよく目にするようになりました
雑穀は、現在人が不足しがちなビタミン・ミネラル、食物繊維が豊富に含まれ、ごはんに加えて炊くだけで手軽に栄養を補給できる、天然のサプリメントのような食材です。
食物繊維は腸内環境の改善に役立ち、免疫力を高めてくれます
また、雑穀に含まれる抗酸化物質のポリフェノールやルチンなどは、活性酸素を除去し、高血圧、脂質異常症の予防につながります
■雑穀に含まれる健康成分のパワー
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
【善玉菌を増強】
腸まで届いたでんぷんや難消化性でんぷん、水溶性食物繊維が、善玉菌のエサになります。
【腸をお掃除】
不溶性食物繊維が不要なものを絡め取り、蠕動運動を促します。
【腸壁の強化】
でんぷんや食物繊維から生まれる酪酸には、腸細胞の生まれ変わりを促す作用があります。
【ダイエット効果】
腸内で産生される短鎖脂肪酸の一種「プロピオン酸」が、脂肪の燃焼を促します。
また、豊富なマグネシウムが代謝を促進します。
【アンチエイジング】
雑穀の胚芽や外皮に含まれるフェルラ酸などの抗酸化成分が、細胞の老化を予防します。
■感染症や呼吸器の病気にも有効?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
玄米や雑穀などの全粒穀物の摂取量が「1日あたり90g」増加すると、感染症や呼吸器の病気の死亡するリスクが低下するというデータが、医学誌で発表されています。
ちなみに、全粒穀物を1日90gとるには、玄米ご飯なら「お茶碗1杯と1/3くらい」です。
出典 BMJ. 2016 Jun 14;353:i2716.(BMJ:英国医師会の医学誌)
(参考)https://www.bmj.com/content/353/bmj.i2716
雑穀は、自然の恵みを丸ごとしっかりいただける食材です。
ごはんに加えて炊くだけでなく、おかずのかさを増すのに使用したり、食感のアクセントとしてサラダやデザートに活用したり、さまざまなアレンジもできます。
毎日の食卓に、雑穀の健康パワーをとり入れてみてはいかがでしょうか。
それでは、今回のレシピをご紹介します。
------------------------------
■チョップドサラダボウル
レシピ写真はこちら↓

(1人分)エネルギー303kcal、塩分1.0g
-材料(2人分)-
・お好きな雑穀:60g
・水:1カップ
-----------
・玉ねぎ:1/2個
・きゅうり:1/2本
・セロリ:1/2本
・ミニトマト:6個
・グリーンリーフ:1枚
・くるみ:お好みで
-----------
・オリーブオイル:大さじ2
・レモン汁:大さじ1
・塩:適宜
・グリーンオリーブ:4~8個
・クレソン:2本
-作り方-
1. 雑穀は分量の水に30分以上浸しておきます。そのまま火にかけ沸騰させてから、弱火で10~15分ゆでて10分蒸らします。
2. 玉ねぎ、きゅうり、セロリは1センチ角に刻みます。ミニトマトは4つ切りにします。
グリーンリーフは一口大にちぎります。くるみは粗く刻みます。
3. "1"と"2"を、オリーブオイルとレモン汁で和えて、塩で味を調えます。
4. 器に盛り、グリーンオリーブとクレソンを添えます。
-ポイント-
雑穀はビタミンやミネラル、食物繊維が豊富!生活習慣病を予防し、便秘や肌荒れの解消、肥満予防にも。
雑穀を準備するのが大変…という方は、白米に入れて炊くだけの市販の雑穀ブレンドがオススメです。
健康サロンかおりのHPはこちら
http://k-kaori-bshs.com/
アメブロはこちら
https://ameblo.jp/kenkousaronkaori/
Facebookはこちら
https://www.facebook.com/kenkousalonkaori/
ラインはこちら
https://line.me/R/ti/p/fAAFkGGB_F
インスタグラムはこちら
https://www.instagram.com/salonkaori_genmaikoso
------------------------------
2020年03月17日
免疫力アップの強い味方!野菜のファイトケミカル★レシピ「きりざい」

免疫力を高めることが大切なこの時期、積極的に取りたいのが“ファイトケミカル”です。
日本での消費量が減少している野菜には、ファイトケミカルという健康維持・増進に役立つ成分が含まれています。
今回は、免疫力アップの強い味方、ファイトケミカルについてご紹介します。
■ファイトケミカルとは
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ファイトケミカルとは、野菜・果物・穀物に含まれる植物性化学物質。
ポリフェノール、イオウ化合物、カロテノイド、糖関連物質などに分類されます。
ファイト(phyto)は植物、ケミカル(chemical)は化学成分という意味です。
トマトの赤色の素であるリコピン、たまねぎの辛味であるケルセチン、ごぼうのアクとなるクロロゲン酸など、食材に含まれる色素や香り、苦味、辛味、渋みやえぐみといった要素もファイトケミカルの一種です。
玄米に含まれるIP6、フェルラ酸、γオリザノールもファイトケミカルの一種です。
■ファイトケミカルの機能
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
にんじんに含まれるカロテノイドは、ウイルスや細菌をブロックする粘膜強化に働きます。
にんにくに含まれるイオウ化合物は強い解毒作用があり、アレルギー症状の緩和や免疫機能をサポートしてくれます。
また最近の研究では、きのこ類に含まれるβ-グルカンが免疫にかかわるNK細胞を活性化するとして、注目が集まっています。
さらにファイトケミカルは強い抗酸化作用を持ち合わせ、免疫細胞を傷つける活性酸素を退治してくれる働きがあります。
加えて、野菜や果物に豊富なビタミンCは、NK細胞を活性化させ、免疫力低下の原因となるストレス緩和にも有効に働きます。
できる限り多様な食材を取り入れることも、機能アップのポイントです。
ファイトケミカルの種類と主な野菜↓
http://www.genmaikoso.co.jp/data/mailmagazine/20200228_03.jpg
■野菜は皮も葉も丸ごと食べる
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
捨てられがちな野菜の葉や皮には、捨てるにはもったいないほどの栄養があります。
また栄養面だけでなく、皮には野菜本来の味や香りもぎゅっと詰まっていますので、おいしさの面からも丸ごと食べる(一物全体食)のがおすすめです。
■野菜の摂取量は減少傾向
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
実は、アメリカ人よりも日本人のほうが野菜の消費量が少なくなっていることをご存知でしょうか。
日本では、肉類・油脂類の消費が増え、野菜や穀類の消費が減少する「食の欧米化」が起きています。
一方、米国では野菜の消費量が増加しており、90年代中頃には日本を上回っています。
○日本の主要農産物の消費動向↓
http://www.genmaikoso.co.jp/data/mailmagazine/20200228_01.jpg
〇日米における1人1年当たりの野菜消費量↓
http://www.genmaikoso.co.jp/data/mailmagazine/20200228_02.jpg
私たちのカラダは食べ物によって培われています。野菜はもちろん、多様な食材をバランスよく取り入れ、免疫力を高めて毎日を元気に過ごしましょう。
それでは、今回のレシピをご紹介します。
------------------------------
■きりざい
レシピ写真はこちら↓

(1人分)エネルギー74kcal、塩分0.7g
-材料(2人分)-
・納豆:50g
・大根:100g
・にんじん:20g
・塩(塩もみ):ふたつまみ
-----------
・野沢菜漬け:50g
・たくあん:20g
・小ねぎ:適宜
-作り方-
1. 大根とにんじんは、納豆と同じくらいの大きさに刻みます。軽く塩もみしてから、水で洗います。
2. 野沢菜漬けとたくあんも、納豆と同じくらいの大きさに刻み、塩分が気になる方は水で洗います。小ねぎは小口切りにします。
3. "1"と"2"を合わせて器に盛ります。
-ポイント-
きりざいは、新潟県の魚沼地方で食べられている郷土料理です。
「きり」は切る、「ざい」は野菜のことで、納豆に細かく切った野菜や漬物を混ぜ合わせたものです。
にんじんに含まれるカロテノイドは、ウイルスや細菌をブロックする粘膜強化に働きます。納豆などの発酵食品は、腸内環境を整えながら免疫力を高める効果が期待できます。
健康サロンかおりのHPはこちら
http://k-kaori-bshs.com/
アメブロはこちら
https://ameblo.jp/kenkousaronkaori/
Facebookはこちら
https://www.facebook.com/kenkousalonkaori/
ラインはこちら
https://line.me/R/ti/p/fAAFkGGB_F
インスタグラムはこちら
https://www.instagram.com/salonkaori_genmaikoso
2019年09月09日
バランスが大事!上手にコレステロール対策★レシピ「こんにゃくとさしみ昆布のサラダ」

コレステロールと聞くと、体に悪いイメージをもたれがち

健康診断での数値が気になるという方も多いのではないでしょうか

そんなコレステロールですが、体にとって必要な脂質のひとつ

大切なのはコレステロールのバランスがとれた状態を保つことです

今回は、コレステロールについての基礎知識と、コレステロールが気になる方の食事と対策をご紹介します

■コレステロールとは?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
コレステロールは脂質の一種。脳や血液、筋肉などに存在し、細胞膜やホルモンの構成成分として重要な物質です。
血中コレステロールが過剰になると、動脈硬化や血栓のリスクが高くなります。
しかし低ければよいというものでもなく、低すぎると細胞膜や血管が弱くなったり、免疫力が低下するなどの弊害が現れます。
■LDLコレステロールとHDLコレステロール
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
血中総コレステロールには【LDLコレステロール】と【HDLコレステロール】があり、それぞれ役割があります。
【LDL(悪玉)コレステロール】
肝臓から血管や組織にコレステロールを運ぶ。
【HDL(善玉)コレステロール】
組織中のコレステロールを肝臓に戻す。
悪玉と聞くと悪者のように思えますが、LDLコレステロールそのものが悪いわけではなく、両者のバランスが崩れてしまうことに問題があります。
そのため現在は、総コレステロール値よりも、LDLおよびHDLコレステロールの比率(LH比)が重要視されています。
LH比は、LDLコレステロール値÷HDLコレステロール値で算出。基準値は2.0以下、2.5以上だと動脈硬化や血栓のリスクが高くなります。
■更年期とコレステロール値の関係
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
更年期になるとエストロゲンというホルモンが減少、その影響でLDLコレステロールを細胞に取り込む受容体も減少するため、血中LDLコレステロールが増え、コレステロール値が高くなります。
体が変化するときは、生活を見直すチャンスです。
変化を受け止めながら、無理なく生活習慣を調整していきましょう。
■コレステロール値が気になる人の食事と生活習慣のポイント
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
1.油脂のとり方を見直す
LDLコレステロールを増やす飽和脂肪酸やトランス脂肪酸(揚げ物、肉の脂身、バターやクリーム菓子など)の摂取を減らし、多価不飽和脂肪酸を含む食品(青背魚、植物油、豆類など)をとるように心がけましょう。
2.主食を玄米、分搗き玄米にする
玄米の胚芽・表皮に含まれるγ-オリザノールという成分は、総コレステロール値やLDLコレステロール値を下げる働きが期待されます。
3.食物繊維をたっぷりとる
食物繊維は余分なコレステロールの排泄を促してくれます。(野菜類、海藻類、きのこ類など)
4.抗酸化成分をとる
LDLコレステロールの酸化は動脈硬化の進行を早めます。
抗酸化力の高い食品を取りましょう。(玄米、緑黄色野菜、海藻類、大豆、ごま など)
5.食べ過ぎに気をつける
過食を避けて、体重管理に気をつけましょう。
よく噛んでゆっくり食べることも大切です。
6. 適度な運動を
運動はHDLコレステロール値を改善します。階段を積極的に使う、待ち時間につま先立ちをするなど、普段の生活に運動を“ちょい足し”するのもオススメです。
食事と対策について、もっと詳しく知りたい方はサイト「ケアごはん」をご覧ください。
https://caregohan.jp/sickness/cholesterol.aspx
■コレステロールと中性脂肪は違う?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
中性脂肪とコレステロールは混同されがちですが、体内での働きは全く異なります。
中性脂肪は血液の流れに乗って全身に運ばれてエネルギーになる一方で、コレステロールはホルモンや胆汁酸の材料となり、主に細胞を構成する成分のひとつでエネルギーにはなりません。
ただし、どちらも過剰になると脂質異常症につながるという共通点をもっています。
コレステロールは私たちの体に必要不可欠なものです。
食生活と生活習慣に気を付けながら、バランスを保っていきましょう。
それでは、今回のレシピをご紹介します。
------------------------------
■こんにゃくとさしみ昆布のサラダ
レシピ写真はこちら
↓

(1人分)エネルギー67kcal 塩分1.4g
-材料(4人分)-
・こんにゃく:80g
・さしみ昆布:5cm角2枚
・切干し大根:30g
・にんじん:少々
・サラダ菜:適量
-----------
【A】
・醤油:大さじ2
・水:100~150cc
-----------
【B】
・酢:30cc
・昆布だし:15cc
・醤油:小さじ1
・白煎りごま:20g
-作り方-
1. さしみ昆布は水で戻してからほぐします。
切干し大根は、水で洗って食べ易い大きさに切ります。
にんじんは、斜めせん切りにして蒸し煮にします。
2. こんにゃくは、せん切りにして湯通ししてから【A】で煮ます。
3. 【B】を合わせて、"1"と"2"を加えて混ぜ合わせます。
サラダ菜を乗せた器に盛ります。
-ポイント-
食物繊維がたっぷりとれるサラダ。食物繊維は余分なコレステロールの排泄を促してくれます。
材料の昆布だしは、さしみ昆布の戻し汁を使用すると便利です。
健康サロンかおりのHPはこちら
http://k-kaori-bshs.com/
アメブロはこちら
https://ameblo.jp/kenkousaronkaori/
Facebookはこちら
https://www.facebook.com/kenkousalonkaori/
ラインはこちら
https://line.me/R/ti/p/fAAFkGGB_F
インスタグラムはこちら
https://www.instagram.com/salonkaori_genmaikoso
2019年06月25日
発酵食品について考えてみましょう★レシピ「軽石揚げ」

毎日暑い日が続いておりますが如何お過ごしでしょうか

今週からいよいよ梅雨入り・・・ジメジメとした蒸し暑い日が
続きますね

かんずり うるか へしこ しょっつる めふん
これらは全て、日本の発酵食品の名前です。
“菌活”という言葉が使われている現在、改めて発酵食品について考えてみましょう。
■発酵文化=知恵の結晶
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
微生物が人間に役立つ働きをしてくれることを「発酵」といい、食材を発酵させたものを「発酵食品」といいます。
発酵食品は、先人たちが「傷みやすい食品をいかに保存するか」「不足する栄養素をいかに補うか」を必死に考え、
経験から発酵を利用してきた知恵の結晶です。
発酵によるメリットには、
(1) 保存性が高まる
発酵により生まれる乳酸や酢酸、アルコールなどには殺菌効果があり、保存性が高まる。
(2) おいしくなる
発酵によりアミノ酸など様々な成分が生まれ、独特の味と香りが加わる。
(3) 栄養価が大幅アップ
食品の栄養成分が増加、さらに新しい成分が生まれ、消化吸収もよくなる。
などがあります。
そんな発酵食品を生み出す微生物(菌)は、気候やその土地の生態系で大きく異なります。
日本は、独自の菌「麹菌(こうじきん)」が中心の発酵食品が豊富です。
■日本のおもな発酵食品
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
日本で全国的に普及している発酵食品として、【醤油/味噌/甘酒/塩麹/醤(ひしお)/みりん/酢/納豆/梅干し/ぬか漬け(漬物)/日本酒/焼酎】などがあります。
これ以外にも、地域によって様々な発酵食品があります。
★日本地図でみる発酵食品いろいろ(一例)
http://www.genmaikoso.co.jp/data/mailmagazine/20190618_01.jpg
■発酵菌の種類いろいろ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
人間にとって"有益"な働きをしてくれる微生物(菌)には、様々な種類があります。
★発酵菌の主なカテゴリー
http://www.genmaikoso.co.jp/data/mailmagazine/20190618_02.jpg
【麹菌(こうじきん)】
日本独自の菌で、味噌や醤油、酒などの日本の伝統食品の発酵・醸造になくてはならない日本の「国菌」。
デンプンやタンパク質を分解する酵素など、多種多様な酵素を大量に作り、体外に出す作用がある。
【酵母菌(こうぼきん)】
空気中や土の中、果物の表面などあらゆるところにいる。
代表的なのはパン酵母で、糖分を分解して二酸化炭素とアルコールに変える。
【乳酸菌】
食品に含まれる糖類から乳酸を大量に作り出し、酸性の環境にして他の菌の増殖を抑える。
漬物やヨーグルトが時間とともに酸っぱくなるのは、乳酸菌の発酵が進むため。
【酢酸菌(さくさんきん)】
発酵によってアルコールを酢に変える菌の総称。酢は酒から造られ、
米が原料の日本酒からは米酢、ワインからはワインビネガーが造られる。
ちなみに、独特の食感を持つナタデココも酢酸菌を利用した発酵食品。
【納豆菌】
納豆を作る際に欠かせない菌。稲わらに棲み、繁殖力が高く熱にも強い。
■発酵食品は究極の身土不二
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
【身土不二(しんどふじ)】という言葉をご存知でしょうか。
身土不二とは、「自分の身体と土は一体であり、自分の住んでいる国、土地でとれた旬のものを食べよう」という考えです。
玄米酵素が提唱する食のかたち「食事道」の基本、「食の三原則」の一つでもあります。
その土地の気候風土の中で生きている菌がつくる「発酵食品」は、身土不二そのもの。
発酵食品は、遠い昔からわたしたちの健康と食の豊かさ支えてくれている、日本の食文化になくてはならない存在ですね。
それでは、今回のレシピをご紹介します。
------------------------------
■軽石揚げ
レシピ写真はこちら

(1人分)エネルギー240kcal 塩分0.5g
-材料(6人分)-
・木綿豆腐:2丁
・納豆:100g
・黒煎りごま:大さじ1
-----------
【A】
・にんじん:60g
・干し椎茸:3枚
・長ねぎ:1/2本
・油:少々
-----------
・卵:1個
・塩:小さじ2/3
・パン粉:1/2カップ
・薄力粉:大さじ1
・揚げ油:適量
・大根おろし:適宜
-作り方-
1. 豆腐は熱湯にほぐし入れ、ざるにあげ、水気をきっておきます。
2. 【A】をみじん切りにし、サッと炒めます。塩少々をふります。
3. "1"の豆腐に卵を加え、すり鉢でよくすり、塩を加えます。
4. "3"に"2"の野菜と納豆と黒煎りごまを加えて混ぜます。
硬さをみながらパン粉と薄力粉を混ぜます。
5. "4"の種をスプーンで落としながら、油でカラッと揚げます。
-ポイント-
納豆と豆腐をまるめて軽石のように揚げたのが名前の由来。
外側はカリッと、中身はフワッとした仕上がりです。
たんぱく質とビタミンB群、納豆のフィトエストロゲンで骨粗鬆症予防、さらに老化防止と更年期障害の予防にも◎
健康サロンかおりのHPはこちら
http://k-kaori-bshs.com/
アメブロはこちら
https://ameblo.jp/kenkousaronkaori/
Facebookはこちら
https://www.facebook.com/kenkousalonkaori/
ラインはこちら
https://line.me/R/ti/p/fAAFkGGB_F
インスタグラムはこちら
https://www.instagram.com/salonkaori_genmaikoso


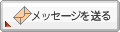
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン